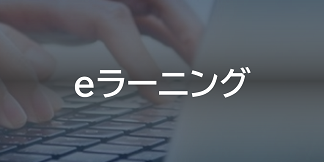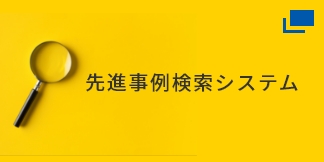ワークライフマネジメントの実践
誰もが生き生きと安心して働くことのできる職場を目指して
JFMでは、性別、年齢、障がいの有無等に関わらず、多様な背景を有する人材が、それぞれの有する知識・経験を相互に共有し高めあい、能力を最大限に発揮することのできる職場環境を提供しています。
多様な働き方を実現する制度
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 勤務時間の選択 | 勤務時間は原則9:00~17:45ですが、必要に応じて勤務時間帯の変更が可能です。 |
| テレワーク(在宅勤務)制度 | 月に10日まで自宅、BCP拠点、サテライトオフィス(横浜市青葉区)、 帰省先(実家等)などでのテレワークが可能です。 テレワークは時間単位でも行うことができます。 ※職場のPCとは別に、テレワークを行うためのPCを1人1台貸与しています。 |
| 年次有給休暇の取得促進 | 最大20日/年(4月新入職員は15日/年)が付与され、時間単位や半日単位での取得も 可能です。 1年で消化できなかった分は翌年に繰り越す制度もあります。 【参考】年次有給休暇取得率: 86.0%(2024年実績) |
| ノー残業デーの徹底 | 毎週水曜日をノー残業デーとして設定し、メリハリのある働き方を推進しています。 【参考】月平均所定外労働時間: 16時間(2023年度実績) |
育児/介護と仕事の両立を支援する制度
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 育児休業の取得 | 子どもが3歳になる日の前日まで取得が可能です。 |
| 育児時間/育児短時間制度 | 未就学児の子がいる職員は、1日の勤務時間を短縮することができます。 |
| 介護休暇/介護時間制度 | 介護が必要な職員は、最大6ヶ月の範囲内で介護のための休暇が取得可能です。 また、介護が必要になった時から3年間、1日の勤務時間を短縮することができます。 |
| 男性の育児休業 | 子どもが3歳になる日の前日まで育児休業が原則2回まで取得可能です。 これとは別に、子どもの出生日から一定期間内であれば「産後パパ育休」としてさらに2回まで育児休業が取得できます。 このほか「育児参加のための休暇制度」も整備し、男性職員の育児参加を促進しています。 【参考】男性の育児休業取得率: 100%(2023年度実績) |
| 子の看護休暇/ 介護のための特別休暇 |
未就学児の子がいる職員及び介護を行う職員は、年に5日の範囲内で看護のための休暇(有給)の取得が可能です。 |
| 育児・介護を行う職員の時間外勤務等の制限 | 育児や介護を行う職員について、深夜勤務及び時間外勤務の制限をする制度です。 |
※このほか結婚休暇、不妊治療休暇、配偶者同行休業など、様々な休暇や休業制度が整備されています。
※上記の制度は、2025年3月時点のものです。
各種制度を利用した職員の声
育児休業から復帰した男性職員
育児休業は、どのくらいの期間取得しましたか?
2023年4月から2023年7月まで、約3箇月取得しました。子どもは2人目ですが、1人目のときは育児休業を取得しなかったので、私にとって初めての育児休業でした。
育児休業を申し出たとき、周りの反応はいかがでしたか?
事前に上司に「育児休業を取得したい」と相談したところ、「おめでとう!育児を楽しんでね」と応援してもらえました。また、福利厚生の担当者から、丁寧に育児休業制度の説明をしてもらえました。周りの理解と充実した制度のおかげで、安心して育児休業を取得することができました。
育児休業中は、どのように過ごしましたか?育児休業を取得して良かったことは何ですか?
上の子の保育園の送迎や、家事全般、夜中のミルクなどを担当していました。日々成長する子どもの側にいられたこと、産後で大変な妻のサポートをできたこと、どちらもとても良い経験となりました。育児休業を取得したことで、家族の仲が深まったと感じています。
JFMでは勤務時間を短縮する制度も整っていますので、今後も必要に応じて制度を活用したいと考えています。
育児休業を取得中の女性職員
育児休業はいつから取得していますか?
2022年7月から育児休業を取得しており、復帰は2025年5月を予定しています。JFMでは子どもが3歳になるまで育児休業を取得できるので、その制度を最大限活用しています。
約3年間の育児休業を取得しようと思った理由は何ですか?
育児休業の取得のタイミングで、夫の地方への転勤が決まったからです。東京で一人で子育てすることもできたかもしれませんが、育児休業をしっかり取得し、家族全員で暮らすことを選択しました。自然の恵みを感じられる環境で家族そろって生活ができ、子どもにとっても、自身にとっても、人生における豊かな経験となりました。
約3年ぶりに職場に復帰することに不安はありますか?
もちろん不安はあります。「仕事を休んでいた間の変化に、しっかり対応していけるだろうか」という心配があります。ただ、数年前にも育児休業からの復帰を経験しましたが、その際も周りが温かく迎えてくれました。また、子育て真っ只中の先輩たちからのエールも、心強く感じています。
JFMは、「仕事と家庭の両立」に理解がある職場です。だからこそ、今回も育児休業を約3年間取得しようと決断できたのだと思います。復帰した後も、育児に関する制度(短時間勤務等)を活用し、家族と協力しながら「仕事と家庭の両立」を目指したいです。
育児のため時短勤務をしている職員
現在、どのような制度を利用していますか?
1日の勤務時間を短縮できる制度を利用して働いています。保育園のお迎え時間の都合で、勤務終了時間を2時間早めています。
テレワーク(在宅勤務)制度も活用していますか?
はい、活用しています。保育園の送迎は夫と分担しているのですが、急遽夫が対応できなくなったときは、テレワークに切り替えることもあります。
JFMでは、テレワーク用のノートPCと携帯電話が1人1台貸与されており、状況に合わせてフレキシブルに働くことができるのが魅力の1つだと思います。
仕事と子育てを両立させるために必要なことや、心がけていることは何でしょうか?
子どもが小さいうちは、仕事をしながら保育園の送迎をしたり子どもの急な体調不良に対応したりすることになりますので、育児に関する制度の活用は必須だと感じています。
また、仕事と育児を両立させるためには、職場のサポートが必要不可欠です。そのため、日頃から上司や同僚とはしっかりとコミュニケーションを取り、仕事の進捗状況などを共有しておくことを心がけています。